福祉は、ときに制度や
仕組みを大切にするあまり、
耕していない土壌のように、
かたく、閉じてしまうことがあります。
私たち「虹の会」は、
そんな福祉そのものをたがやし、
地域にひらかれた風通しの
よい場をつくりたいと考えています。
それは、障がいのある・なしを問わず、
一人ひとりが、その人らしく、
文化的に生きていくために。

土壌をたがやし、種や苗が育ち、
花や実を養うように。
互いに心をたがやし、
ひらいていくことが、
文化的に豊かな状態なのだと思います。
ここに集うもの同士が、
共に生きるために、
晴れの日も、雨の日も、
「おたがいさま」といえる
つながりを育み、
暮らしをつくる。
私たちは、そのような“福祉の耕作者”で
ありたいと願っています。

虹の会は2026年に
30周年を迎えます。
滋賀県高島の地に根をおろし、
虹の会は、おたがいさまの気持ち
を大切に
歩んできました。
特別なことを
してきたわけじゃありません。
ただ、そばにいる。
声をきく。手をとる。
そんな日々を、重ねてきた30年。
これからもこのまちで、
人と人のあいだに
芽生えるつながりを、
ていねいに育てていきます。
ロゴを
リニューアルしました。
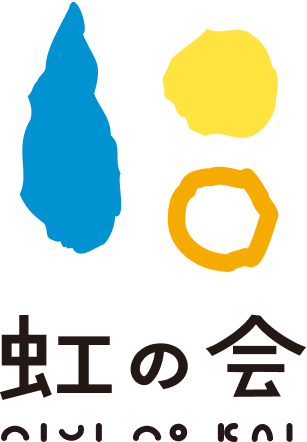
虹の会のロゴは、「虹」があらわれるための要素の「雨粒」「太陽」「人」をモチーフに取り入れています。
雨粒は困難や試練を、太陽は希望と光を、そして人は私たち一人ひとりの存在の尊さを表現しています。どのような困難も、ともに支え合うもの同士が、その先にある光を見つめることで乗り越えていけるものだと思います。
虹の会が
育んできたこと

子どもから
お年寄りまで、
ずっとそばで支える
「私たちがいなくなったら、この子はどうなるのか……」障がいのある子を育てるご家族が、ふとこぼした言葉です。その問いに、虹の会は応えたいと思い、障がい者支援に限らず、暮らしから余暇、働き方の多様性まで、人の一生をまるごと見つめて支えたいと考えてきました。ひとは、ひとりで生きられない。けれど、それは弱さではなく、つながりのかたちです。私たちは、その関係性をたがやす、つながりの土壌です。

まちの声に応えて、
広がっていった拠点
虹の会が大切にしてきたのは、時代ごとの声に耳をすませることでした。まちの小さな「困りごと」に寄り添ううちに、ひとつ、またひとつと拠点が生まれ、高島のまちにぽつぽつと灯を灯しています。大きな拠点をつくるより、小さな灯をたくさん灯すほど、まちは温かくなるはずです。私たちは、困りごとをキャッチするための「気づきの網」を繕いながら、孤立しないまちを紡いでいきます

たしかな専門性と、
心を込めた支援
知識や資格は、私たちの大切な道具です。けれど、それだけでは届かないものが、人と人の間にはあります。支援は、マニュアルではなく、関係の中に息づくもの。虹の会の職員は、その日、その時の小さな発見を共有し合い、支援のかたちそのものを育てています。ときには、支援する側が利用者に励まされることも。そこに生まれる「おたがいさま」の往復こそ、私たちの専門性のいちばん深いところにあるものです。
\おたがいさま/な
わたしと虹の会
支える人と支えられる人。その立場に関係なく、
そのあいだに「おたがいさま」が芽ばえるとき、福祉はたがやされていきます。
虹の会の日常にある声をひろいあげてみました。
サービスと事業所
相談する

福祉って想像力なんです。 わたしたち福祉に関わる職員に必要なのは、想像力です。相談窓口に電話をくださった方は、どんな気持ちだろうか。1本の電話をかけるまでにどれだけ迷いがあったのだろうか、と想像しながら受話器を取っています。だから、相談のたびに何かひとつでもお土産になるような話をしたいんです。
どんなお困りごともまずは受け止める
福祉って、だれかを支える仕事だと思われがちです。でも、支える前に、まず「聴く」。それが、すべてのはじまりです。「どうしよう」という、まだ形にならない不安や言葉にならない願い。そこに耳をすませることが、福祉のいちばん手前にある仕事です。私たちは、障がいのある方や社会になじめない方の“暮らしの地図”を共に描いていきます。その人が歩きたい道を聴きながら、たくさんの支援の中から、いちばんその人らしいルートを探していく。ときに教育、医療、地域などを行き来し、その人の暮らしが無理なくつながるように計画します。
暮らす

ひとりで生きることより、
居場所をたくさんつくりたい。
たとえば、震災が起きたとき、利用者さんに手を差し伸べられるのは自分たち職員ではなく、地域の方かもしれません。そう考えると、自立とは誰かに頼らずに生きることではなく、暮らしのなかに、いくつもの“頼れる場”を持てることだと思います。そんな「関係の輪」を広げていきたいです
自分らしく暮らすために
一人ひとりの自立を支援
その人らしい暮らしをつくるには、その人の“できる”を信じることが大切です。虹の会では、利用者の方が地域のなかで安心して暮らせるように、いくつものグループホームを運営しています。そこは「守る場所」ではなく、“自立への途中”にある共同生活の場です。自分で選び、自分で決めて、喜びも悔しさも、ちゃんと自分のものとして生きる。そばで信じることが、寄り添うことの第一歩だと思っています。また、住み慣れた家での生活を続けたい方には、居宅介護や外出時の付き添いを行う行動援護など、状況に合わせたサポートを行っています。
過ごす
はたらく

ひとりの人間として
その人の性格に合わせた支援を。
当然のことですが、障がいのある・なし以前に、ひとりの人間としてその人の性格があります。日中活動時の声のかけ方ひとつをとっても、その人の性格に合わせたアプローチを心がけています。虹の会は活動内容の幅が広いので、個々にあった過ごし方を見つけてもらえたら良いなと思います。
働くこと、過ごすことこそ
その人の人生のかたち
どんな人にも、その人だけの時間があります。虹の会では、子どもから高齢までの利用者の方が、自分のペースを保ちながら段階的に社会とつながりをもてるよう、さまざまな通所サービスを展開しています。「働く」を支える就労継続支援では、複数の拠点があり、その人の得意や状況に合わせて働く場所を選び、できることを少しずつ広げたりします。
「過ごす」を支える生活介護では、食事や身の回りの介助を含めながら、その人の“暮らしのリズム”をともにつくっていく。なにより「その人が、その日をどう過ごしたいか」をいっしょに考えています。また、農作業や自主製品の制作活動を通じ、生活介護で働くといった活動も行っています。
高島には、急がない時間が流れています。
高島って
こんなところ
「高島には、余白があります」これは、ある職員の言葉です。
びわ湖のきらめき、森の静けさ、田園風景に響く鳥の声。
このおおらかさな風土が、
誰かを待つ気持ちや、支え合う間合いを育てているのかもしれません。
あなたも虹の会で
働きませんか?
虹の会で働くことは、誰かとともに、生きる風景をたがやすこと。
いま、そんな仲間を探しています。

虹の会で働く人
職員の1日や、虹の会での仕事に関するインタビューを紹介します。

採用情報
募集要項、採用に関する問い合わせはこちらから。
田村理事長に聞いた、
「おたがいさま」の
ある暮らし

- 田村理事長が「おたがいさま」を感じる場面は?
-
法人の方針・目標を掲げ事業に取り組むにあたり、管理職とベクトルを合わせていきます。また、課題に対して管理職間の連携や協力関係の中で解決に向かうこともたくさんあります。立場や役割が違っても、ベースにあるのは「おたがいさま」のつながりであり、大切にしている思いです。
- 過去には限界集落への支援活動に力を入れていたと聞きました。
-
障がいがある方もない方も、ともに地域のなかで働き、暮らせる社会を目指して2011年に開始したのが、移動商店街「ぎょうれつ本舗」です。買い物が困難な山間部や過疎集落へ出向き、利用者さんがスタッフとなり、パンや焼き菓子、お惣菜などの食料品、日用品の販売を行いました。

《ぎょうれつ本舗は、その名の通り、移動販売車が行列をなして過疎集落を回る。買い物が困難な方への支援と障がいのある方が地域社会で働く先進的な取り組みとして話題に》 - 『福祉をたがやし、「おたがいさま」のつながりを育てる。』のメッセージに込めた思いを聞かせください。
-
困ったときは“おたがいさま”。気軽にそう言える温かい心が人とのつながりを広げていくと思います。福祉制度の受け皿という役割だけではなく、虹の会という拠点をひらき、「地域の人と一緒に」活力ある地域を築くきっかけづくりをしていきたいです。
- 田村理事長にとって福祉ってなんですか?
-
人によって幸せの形は違いますが、一人ひとりの命や権利が守られ、人や社会とのつながりのなかで幸せに生きていける地域をつくっていくこと。それを特別なことだと思わず、ふだんの暮らしのなかで自分事として考えたり、ちょっとやってみる、そんなことが広がれば福祉が身近になっていいなと思います。




























